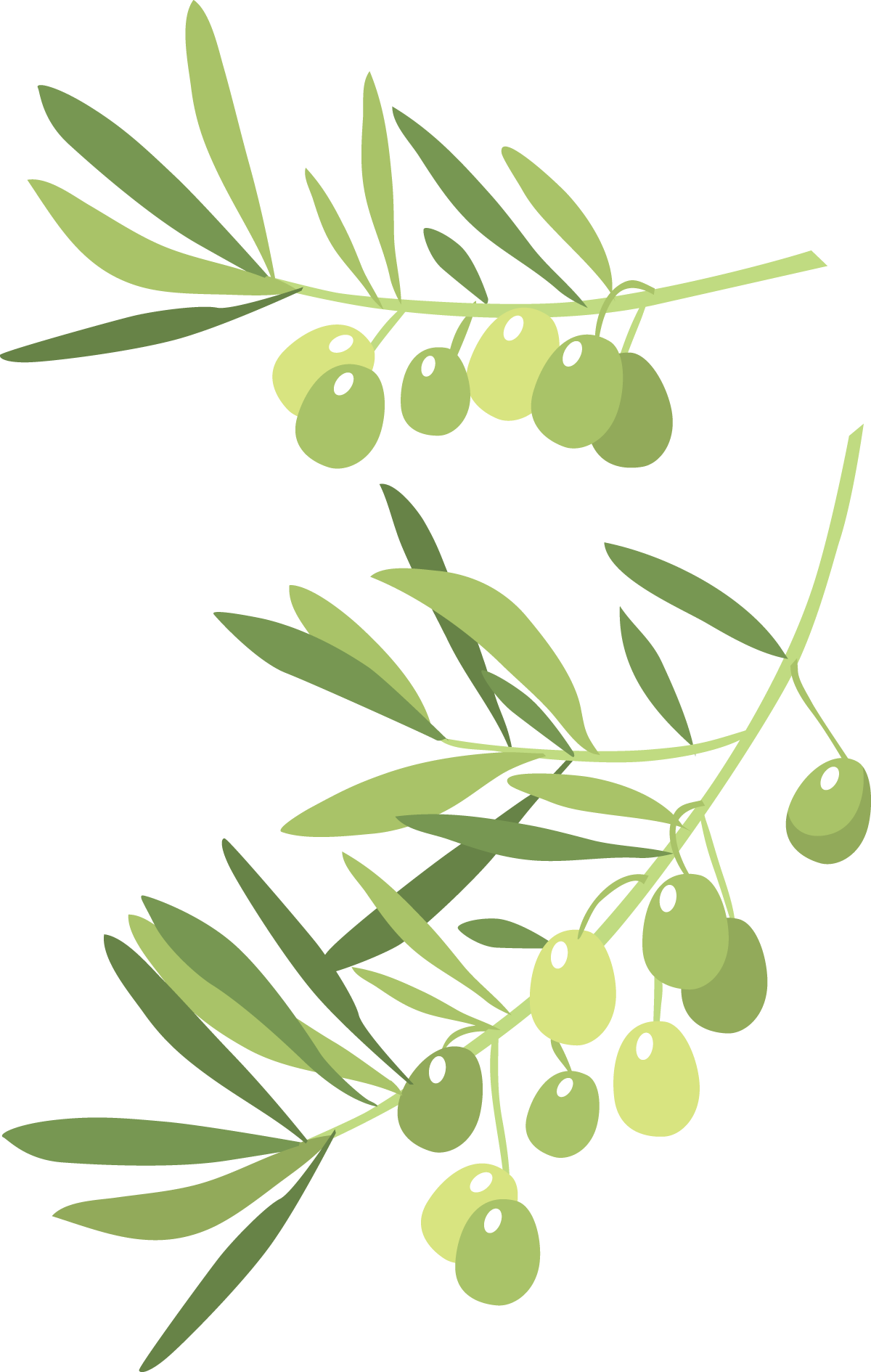私が4歳の時から話は始まる。私の家庭には障害者手帳を持っている人間が複数いる(いた)んだけど、一番最初に障害者になったのは父だ。半世紀も前のことではあるけれど、まだ存命な人達も登場するので、完全なノンフィクションではない。少しフェイクをかけてある。でも、大体こんな感じのことが私の周りでは起こり、それを見聞きして成長した。
私が「お嬢様」と呼ばれていた時代
はまち は貧乏人の食べ物だと父は笑った
鮮明に覚えていることを1つ書いてみようと思う。
父は私をよく寿司屋に連れていってくれた。当時は回転ずしなどない。職人さんが客の注文を聞いてから握る、いわゆる「回らない寿司屋」だ。
「お嬢様に次は何を握らせていただきましょうか」
うやうやしく職人が父に声を掛ける。すかさず私は「はまち!」と大声で注文。父は困った顔をしてこう言うのが常だった。
「カッコ悪い子やなあ。なんでそんな安モンばっかり頼むんや」
私は食欲旺盛でよく食べた。苦くてあまり好きじゃないものもあったけど、「食べなさい」と言われてしぶしぶ食べたものもある。ウニだったのかもしれない。
父と2人だけのこともあったけれど、知らないおじさんが一緒だったこともあった。有名な人だったんだと分かったのはもう少し大きくなってからだ。大人が見るニュースを見るようになって、あのおじさん達がどういう人達だったのかを知った。
どうやってそんな人とコネがつながったのかよく分からない。父はとてもアグレッシブな野心家だったので、手段を選ばずグイグイと色んなところに入り込んでいったのかもしれない。
病が我が家を飲み込み始めた頃
父が服用していたのはてんかん薬
父は精力的に働き豪快に呑む人だった。その一方で、毎食後に沢山の薬を服用していた姿も覚えている。なぜそんなに沢山の薬を飲んでいるのかと尋ねた。元気な人は十種類近くも薬を飲んだりしないはずだ、と。
返ってきた答えは「元気になる薬だ。お仕事が忙しいからね」だった。
しかし後になって分かった。それらは抗けいれん剤と呼ばれる薬で、要するにてんかん薬だということが。
若い時からずっと薬を飲んでいたおかげで、社会に出る頃には一度も大きな発作を起こさなくなったのだという。しかし発作の原因は分からぬままだった。
とにかく薬を飲んでいれば症状が出ないので、対処療法的にずっと薬を飲んでいた。
脳動静脈奇形があります 覚悟して下さい
大きな病院できちんと検査を受けた結果、脳内に脳動静脈奇形という異常があると分かったそうだ。その奇形が原因で父はてんかん発作を起こしていたらしい。
治療は開頭手術のみ。確実に身体障害者になる。しかもどの程度の障害が残るかは、手術してみないと分からない。今の医学では、それが最新の治療法だ。
医師からそう宣告され、両親は突然の不幸を受け止め兼ねて病院から帰ってきた。
あと何十年もの人生を、どの程度不自由な体で生きていかねばならないのか分からない。しかも命を救うためには、身体の機能を差し出すしか道はない。命が助かる方がいいに決まっている。結論は出ていた。心がそれに追いついていかなかった。
こういう事情が分かったのは、私がもう少し大きくなってからのことだけれど。
お父さんがいなくなる。この一言で私は全てを悟った
ある日、私と弟のところに母がやってきた。硬い表情を崩すことなく私達の肩に手を掛けてしゃがみ、静かにこう言った。
「お父さんがいなくなってしまうのと、身体が動かなくなってもそばにいてくれるのと、どっちがいい?」
「いなくなる」という言葉が何を意味するか。私はその時すぐに分かった。
・・ああ。だから最近、脳とか血管とか書いてある本が増えたのか。
私は字を覚えるのが早かったので、父が真剣に読んでいる本が脳血管の病気の本だと気づいていた。誰のために読んでいるのかは分からなかったけれど。
そうか。お父さんの頭の中が病気だったんだ。しかも「いなくなる」かもしれない病気なんだね。身体が動かなくなったお父さんの姿は全く想像できない。
けれど、選択肢がこの2つしかないのなら。答えは1つだ。覚悟を決めて返事をした。
「生きていて欲しい」
母はかすかにうなづいた。表情が少しゆるんだ。
自分が出した結論が正しいのか。それを医師に告げていいのか。母は誰かに背中を押してもらいたかったんだと思う。それが幼い子供であったとしても。

これからうちは貧乏になる 覚えておきなさい
小さな会社ではあったけれど、父は創業社長だった。障害者になることが確定した段階で、会社をどうするのか色々揉めていたようだ。
私にはその詳細は分からない。聞かない方がいいと思ったし、たとえ聞いたとしても、まだ幼稚園児だった娘に、そんなことを正直に教えはしなかったはずだ。
会社がなくなる。私が理解できたのはそこまでだ。
「これからうちは貧乏になる。覚えておきなさい」
母はきっぱりと私に言った。貧乏というのは、具体的に何ができなくなることなんだろう。よく分からないまま、とりあえずうなづいておいた。
あとから分かったことだが、父は宵越しのカネを持たない系の人だったため、貯金があまりなかったそうだ。病気を持ってるんだから、堅実にお金を残しておけばよかったのに。薬で症状は抑えられているから大丈夫だと思っていたんだろうか。
そんな折に突然「放っておくと破裂して命に関わることになりますよ」と診断されてしまった。あちこち大病院を回って診察を受けたけど、やはり結論は変わらなかった。
あなたたちを預かる気はない
それ以降の時の流れはとても速かった。手術に向けてちゃくちゃくと色んな手続きが進められていく中で、一番大きな問題の一つは、私たち子供の養育だった。
入院・手術が行われる病院は完全看護の病院ではなかったため、手術後もずっと母が病院でつきそいをせねばならない。私の下には3歳の弟もいる。子供だけでずっと家に置いておける年齢ではない。
父方の親戚は関西、母方の親戚は四国にいた。父が直々に「妻の付き添いが不要になるまでの間、子供を預かってくれないか?」と頼んだそうだが、兄弟4人ともそれを断った。
その時のやりとりの一部を私ははっきり覚えている。ひとりのおばさんがこう言った。
「うちはあなたの家のように裕福ではない。小さい子供もいる。これ以上子供の面倒をみることはできない」

当然タダで子供を預かれなどと無茶を言った訳ではないと思う。けれども結果的に私たちは、父方の親戚の家でご厄介になることはできなかった。
血のつながった兄弟が何人もいるのに誰も手をあげてくれなかったなんて。仲がよくなかったんだろうな。
高知行きフェリーの二等船室にて
幼稚園児の「お嬢様」と身体が弱い「おぼっちゃま」は、最小限の荷物を持った母と共に高知行きのフェリーに乗った。穏やかな瀬戸内海航路とは違い、高知行きの船は本当によく揺れた。
粗末な二等船室の床でごろごろ転がされながら、私は古い毛布のケバ立ちを睨み続けていた。
事実は受け入れなければいけない。「はまち」の寿司を安モンだと馬鹿にしていた父は、もう二度と戻ってこない。次に会う時、父はどんな姿になっているのだろう。身体が動かないというのはどういうことなんだろう。
私が世間を疑い、群れるのを嫌い、ものごとを斜に構えてみるようになったのは多分この頃からだ。あなたを預かる気はないからね、という言葉が頭の中でごろごろと転がり続けていた。
●続きはこちらから●
-

脳動静脈奇形の手術を受ける父 知り合いの家をたらいまわしになる子供
続きを見る