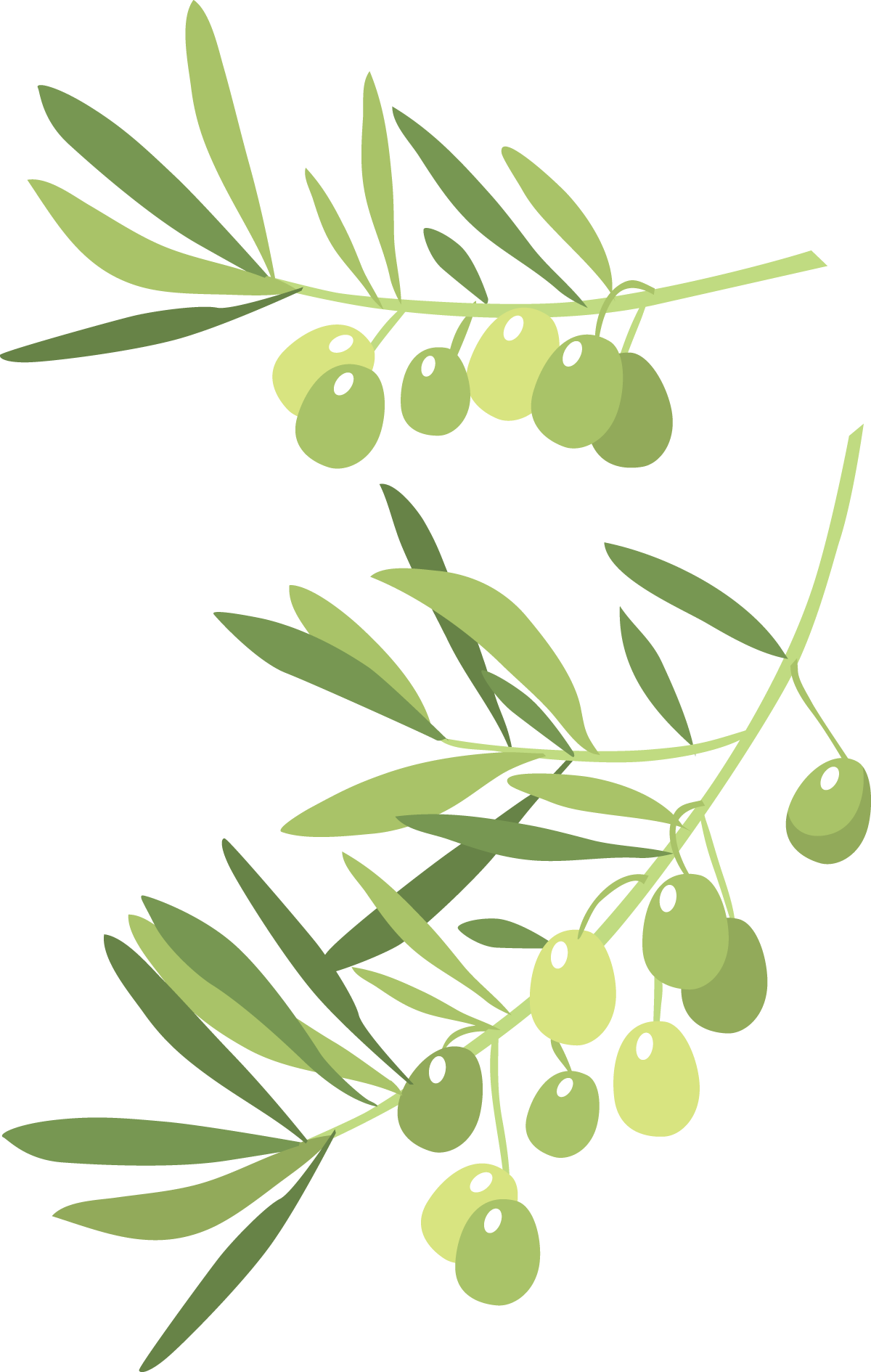父は脳血管手術。母はその付添い。私と弟は親戚の家へ。
しかし、とあることがきっかけになり、私だけがその家から出ていかねばならなくなった。
私は別の親戚のところに送られたけれど、そこにも長くはいられなかった。次の家へ、また次の家へ。預け先が変わるにつれ、うちの両親との縁が薄いところでご厄介になることとなる。たらいまわしって言うんだよなこういうの。どこに運ばれていくのか分からんバケツリレーというか。
何が原因だったのだろう。その家の子とケンカをしたわけじゃない。ご飯のおかわりをしたわけでもない。ものを壊したり盗んだりもしていない。なのになぜ。
次はどこの家に行くんだろう
貧乏な家の子を預かっても何の得もならないもんな。1軒の家に幼い子供が2人も増えたら世話も大変になるもんな。お金がなくなったからこんな目にあうのかも知れない。人を信じたら痛い目にあう。気をつけよう。ただただそう思うしかなかった。
幸いだったのは、3歳だった弟には当時の記憶が一切残っていなかったことだ。
クリスマスブーツの赤は 愛情の色
私はいまこうやって、大昔のことを思い出すことができる。けれど、浮かんでくる光景はみな白黒写真。生き生きとした色のついた記憶がない。唯一はっきりと色を覚えているのは、クリスマスブーツのまばゆい赤。12月に入るとお菓子売り場に並ぶあれのことだ。
私は何カ月お菓子を食べてないんだっけ。去年までは、ぎっしりお菓子が詰まったクリスマスブーツを当たり前のように買ってもらってたな。クリスマスツリーもきれいだったな。「いっぺんに全部食べたら太るから、気をつけるんやで(笑)」と言ったのはお父さんだった。
お父さんお母さん、元気かな。
今年はサンタさん来ないよね。私、知ってるんだよ。サンタさんってお父さんお母さんのことだよね。だから今年はサンタさんは来ない。サンタクロースがいるって信じられる子は、幸せだよね。
サンタはいない。いるのはサタン。
私は言葉を覚えるのが早かったので、言葉遊びをしながら毎日を漂うように生きていた。頭の中なら私も自由に生きられる。自分の気持ちがしっかりしていれば、頭の中は私のものだ。
お腹がすいた もうあかんねん
何軒目の家でのことだっただろう。私は関西のどなたかの家に住まわせてもらっていた。
1日1食の日が続き、肥満児だった私もさすがに痩せてきた。服がぶかぶかになり、袖から裾から容赦なく冷たい風が入り込んでくる。「百貫デブが普通のデブになってよかったやんw」という笑い声も冷たかった。
公園でひとり遊びをすることが多かった。何か食べたい。この公園に何か食べられそうなものは落ちてへんかな。そう思いながら。
ある日のことだ。私はいつものようにお腹をすかせて、枯れ葉を足で蹴りながら歩いていた。ゴミ箱ものぞいてみた。食べられるものがこんなところにあるはずない。そんなことは分かってる。でももう、ただじっと空腹に耐えて座っていられなかったんだ。
色鉛筆の茶色は 空腹の色
そんな時。短い色鉛筆が転がっていることに気付いた。正確にいうと一瞬だけ、その色鉛筆は、包装紙に包まれたチョコレートに見えた。
抑えていた食欲が一気に噴き出した。もう止められない。あろうことか私は、地面に落ちていた色鉛筆を拾ってガリガリとかじりはじめたんだよ。食べもんじゃないことはよく分かっている。でも、口の中に入るものなら何でもいい。これは色鉛筆。ぬりえをするもの。食べ物じゃない。でもおいしそう。でも食べたらあかんもんや。分かってる。
私は泣いた。わーわー泣いた。私はなんでこんなものを食べてるんや?これは色鉛筆。きれいな色やけど食べ物と違う。硬い。いくら噛んでも硬い。お腹がすいた。お腹がすいてるねん私は。
なんでこんなもんを食べてるんや?!
誰かが立っているのに気がついて目腺をあげた。いつも地面の上で暮らしてるおっちゃんが、恐ろしい形相で私を見降ろしてるじゃないか。何? こんな時に何? 私は悲しいねん。もうこれ以上やめてほしいねん。ごめんやけど、おっちゃん怖いねん。
「ドアホ!何を食うとるんや!それが何なのか、お前は分かってるんか?」
私はどこへ行っても怒鳴られる。もう嫌や。こんな生活、もう嫌や。
走って逃げだそうとした私を、おっちゃんの手がガシっとつかんだ。
「怒らへんから言うてみ。おまえはなんでこんなもんを食うとるんや?」
怒らへん? 嘘や。大人は私を怒るもんや。おっちゃんもそうやろ?でも、もう何もかもがどうでもええ。お腹がすいた。私はぽろっと弱音を吐いた。
「・・・お腹すいて私、もうあかんねん。ほんまの家に帰りたいねん。ごはん食べたいねん。お父さんが脳の手術してるねん。お母さんは付添いやねん。弟は遠いとこにおるねん。せやから私、頑張らなあかんのに、もうあかんねん。お腹がすいて、もうあかんねん。」
パンの耳の薄茶は 優しさの色
さらにおっちゃんの顔が険しくなった。
「ちょっと来いお前。聞こえへんのか?来いて言うとるんや!」
有無を言わさず手を引っ張られ、たどり着いた先はパン屋だった。
「色鉛筆よりはマシや。食え」
押しつけるように渡されたのは、パンの耳ばっかりが入ってる袋だった。今思えば、おっちゃんにとって、その数十円は本当に貴重なお金だったはずだ。
見知らぬ人の方が優しいって 悲しいことだね
「そういうたらお前、こんな時間になんで公園におるんや?学校はどないしたんや?」
「おっちゃん、私は小学生とちがうねん。今は通ってないけど、幼稚園生やねん」
「おっきいなあ。3年生くらいかと思てたわ」
「よく言われるわ、大きいって。百貫デブって言われる」
「百貫デブやったんかお前。えらい痩せてるど。これ食え。パンの耳は安いけどウマいど」
皮肉なもんだ。どこの誰だか分からないホームレスのおっちゃんの方が、親戚とか知り合いとかいう人達よりも優しいじゃないか。
おっちゃんには家族がいたみたいだ。小学生の子供がいるって言ってたよ。今は地面にゴザを敷いてひとりで暮らしているけどね。今思えば、おっちゃんは子供に会いたかったんだろうと思う。
みんなみんな 作り話ならいいのにね
作り話だと思われるだろうか。私も思うよ、これが作り話だったならよかったなって。
「ふるさと」という童謡の歌詞を耳にするたび、今でも私は食パンの耳を思い出す。
いかにいます父母 つつがなきや友がき 雨に風につけても 思い出ずるふるさと こころざしをはたして いつの日にか帰らん 山は青きふるさと 水は清きふるさと
両親はどうしているだろう。友達は元気だろうか。雨の日も風の日も、思い出すのは故郷のこと。
やるべきことを果たして、いつか帰る日がくる。山が青々としている故郷へ。水がきれいな故郷へ。
今の自分のが歌詞になっている気がして泣き崩れた。
歌詞の意味が分からない方が幸せだった。
-

小学1年生のひとり暮らし
続きを見る