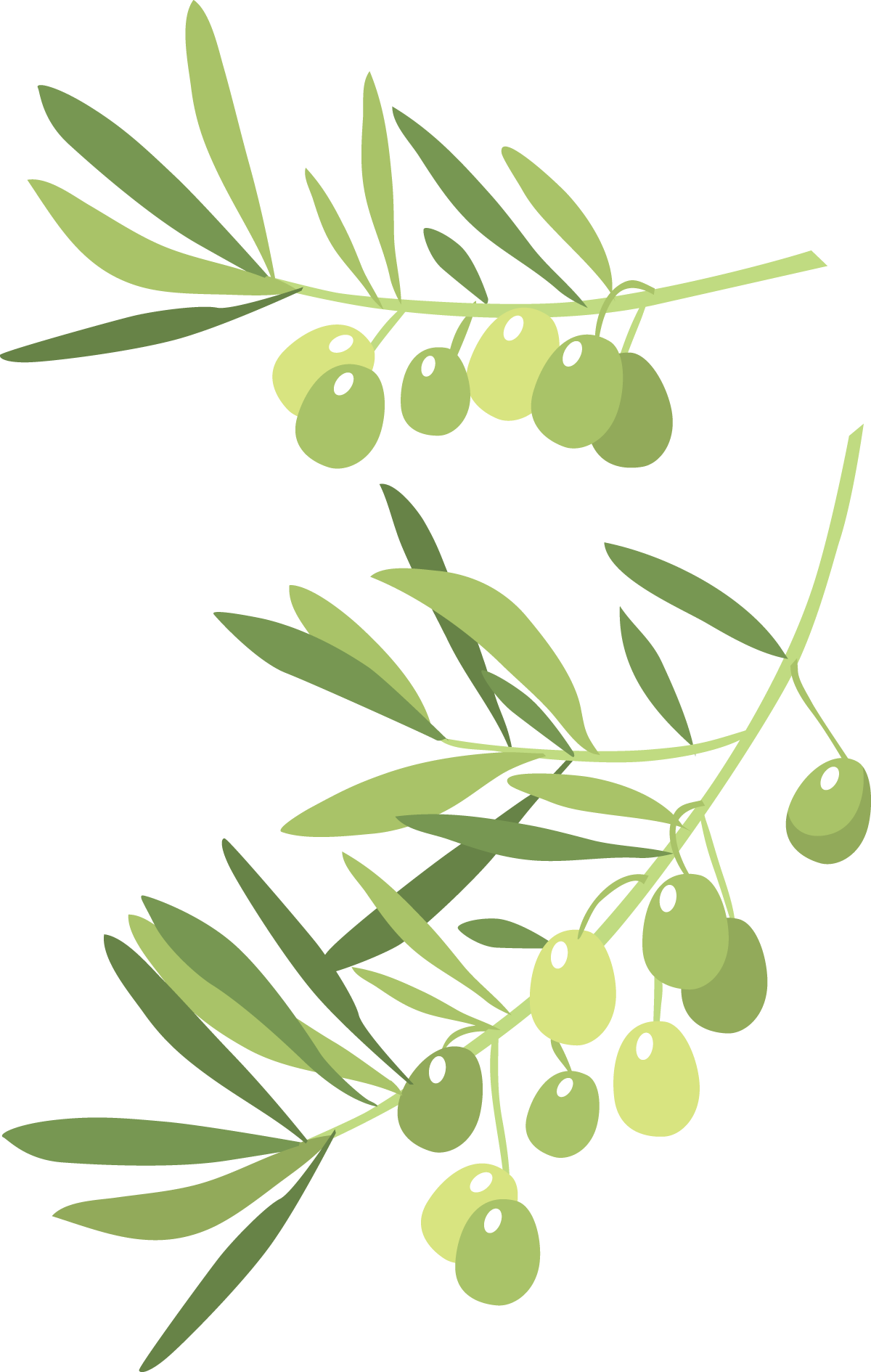「脳出血で突然死するか、手術をして障害者になるか。どちらにしますか」
医師にそう告げられた私たち家族は、実に不本意ながらも手術を受ける決断をした。
そして母は、遠くに住む妹の家に私達を預けることに決めた。「お父さんが退院するまで我慢してや」と私に言い含めて。幼い2人の子供を預かってくれる近くの親戚が見つからなかったせいだ。
母の異母姉妹の家に行く
なぜ父が入院するにあたって、私達を他人に預ける必要があったのか?若い方は疑問に思うかもしれない。入院患者の身の回りの世話は病院がするじゃないか、と。でも当時はそうじゃなかったんだよ。家族や知り合いなどが病院に泊まり込むか、高いお金を出して付添婦を雇う必要があったんだ。
うちには家政婦を頼むお金の余裕なんてない。会社が倒産してしまったんだから。そこで、母が病院に泊まり込むことになった。
当時私は6歳、弟が3歳。ようやく幼児2人を引き受けてくれたのは、遠い所に住んでいる親戚だった。
色鉛筆とお人形さんをつれて
「冬の太平洋航路は荒れるよ」と聞かされていた通り、フェリーは立って歩けないほど揺れていた。ごろごろと毛布ごと転がされて何時間たっただろう。
「降りるで。カバンを持ちなさい」
とうながされ、色鉛筆やお人形さんを入れたカバンを持ち、デッキに出た。冷たくさびた階段めがけて、12月の海風は容赦なくぶつかってきた。沢山の人が下りたはずだ。なのに、フェリー乗り場の建物は、寒くて無機質な場所だったという記憶しかない。
雑踏の向こうに母方のおばちゃんの顔が見えた。年に一度、母と一緒に帰省する時に会うおばちゃんだ。今思いだすと、白黒写真の中で、そのおばちゃんのところだけはカラー写真のように見えていた。
その人と母は、違う女性から生まれた姉妹、異母姉妹ってやつだ。母を産んだ女性は、出産から半年後に腹膜炎で亡くなったと聞いている。その後おじいちゃんは再婚して、再婚相手との間に3人の子供をもうけた。私たちが向かっているのは、その3人のうちのひとりのおばちゃん宅だ。
母とそのおばちゃんも仲はよさそうだった。「お前のおばあちゃんは、お母さんを大切に育ててたんだよ」と多くの人から聞かされていた。それでも、うちの母とおばちゃんやおいちゃんの間には少し遠慮がある。私と弟は、そういう微妙な雰囲気の親戚宅でしばらくご厄介になった。
とんでもないところに来てしまった
数日お世話になった頃、色々ややこしいことが分かってきた。てっきりおばちゃんの旦那さんだと思っていた男性は、他に奥さんと子供がいる人だった。おばちゃんは愛人だったんだ。
時々本当の奥さんが怒鳴りこんできた。甲高い叫び声の方言だ。何を言ってるのか分からない。きっと「主人を返せ泥棒猫!」みたいなことだったんだろう。
ドラマかこれは。なんかすごいところに連れてこられてしまった。
そして おいちゃんが大酒飲みで、一定量を超えたら見事に豹変する人だってことも、ご厄介になっている間に知った。豹変したが最後、大きな酒瓶を握りながら叫んで荒々しく家中を歩き回る。とても体格のいいおいちゃんを少しでもなだめようと、おばちゃんは気をつかいながら懇願するのが常だった。
本当にとんでもないところにきてしまった。なんだここは。この人たちはなんなんだ。
帰りたい。
家に帰りたい。
しかし私たちはここでお世話になるしか道がない。お父さんが元気になるまでの辛抱だ。
事情がよく分かってない弟の笑顔を見ながら、どうすれば嫌われずに過ごせるか、自分なりに毎日考えていた。「面倒なガキだ」と嫌われたら、容赦なく叩き出されて路頭にまようだろう。
弟を隠す盾になろう
今自分にできることは何だ?おいちゃんが暴れるたびにいつもいつも考えた。
私にできるのは、とばっちりで怪我をしないよう弟を庇うことだけだと思った。あいつは身体が弱くて小さい。その一方で、私は年齢の割には身体が大きい。だから盾にならなければいけない。私はお姉ちゃんだから。大きな身体のお姉ちゃんだから。
おいちゃんが酒を飲んで暴れるたびに、弟を壁と背中の間に隠した。そして、大きな男がふるう暴力のすさまじさを一部始終見ていた。
震えながら座っていた。涙は出なかった。泣いてどうにかなる状況じゃない。泣き声がおいちゃんを刺激し、出ていけ!といわれたら最後だ。私は壁の一部。私はいない。だからこっちを見ないで。
泣くな
ある日のことだ。
テーブルにご飯粒を落としたことに気づかず、私は「ごちそうさま」と言ってしまった。その瞬間、おいちゃんが私の肩を激しく揺さぶった。
「食べさせてもらっているご飯を粗末にしやがって!」
おいちゃんの酒は一定量を既に超えていたようだ。
やってしまった・・暴力の矛先がとうとう私に向けられる日が来てしまった。
身体が大きく、愛嬌もなく、甘えることもなく、何があっても泣かない子供。今にして思えば、それは逆効果だったのかもしれない。
私が泣かなかったのは、泣き声がおいちゃんを刺激するのが怖かったからだ。愛嬌どころか、恐怖に耐えるためにこわばっていた顔は、人をにらみつけていたように見えていたのかもしれない。
弟がわんわん泣きだした。
まずい。泣くな。張り倒されるかもしれないんだぞ。でもそんなこと、3歳の子供に分かるはずがない。弟を壁側に押して移動させた。そして封をするように、私は弟の前に座った。
私は盾だ。何があっても私は盾だ。お父さんはもう普通の身体ではいられない。死ぬかもしれないとも聞いている。だから私は盾だ。お父さんがどんな身体になっていたとしても、私は私の家の盾。
盾は崩れ、残骸は外に運び出されていった
しかし、6歳の少女は盾になり切れなかった。ガクガクと肩を揺すられ、あっけなく転がされた。あっけなく崩れた。私は盾にはなれなかった。弟が壁と一緒に固まってるのが見えた。
おとうと、それは私のおとうと、手をあげないで。うちはお父さんが死ぬかもしれないの。お母さんは遠くにいるの。いまここにいるのは私だけ。おとうとは病弱で、ごはんはよく残すし、好き嫌いが激しいし、ごはんを食べさせるのは大変なの。私が食べさせないと、ごはんをちゃんと食べないの。
どうしていいかわからない。もういい。もうたくさんだ。注意をこちらに引きつけないとまずい。ありえない程おおきな声で私は叫び、そして暴れた。
おいちゃんの大きな体の向こうには、ただオロオロと困った顔をしているおばちゃんの顔が見えた。いつもそうだ。今回もそうか。こんな大きな人は怖いよね。気持ちはよくわかるよ。おばちゃん、私も怖いよ。
それから程なくして、盾の残骸は、別の親戚の家に引きとられていくことになる。
心は乾いたスポンジにかわる
ある晩、別の親戚の人がやってきた。語気の荒い酔っ払いの声と、それをなだめる慎重な声が、私達の頭の上を交差する。どんどん雰囲気が険しくなる。「ワシがちゃんと働いたらトイレにもエアコンがつくんじゃけんな!」(つくんだからな!)」とか叫んでる。もうマトモな話し合いができる状態じゃないってことだ。
そして最後に、私の心にトドメを刺す叫び声がした。
「こまい(小さい)のは置いといてやるけんどが、このデカいのは邪魔やけん、持っていんでくれ!(持って帰ってくれ!)」
そうか。やっぱり私は邪魔だったんだな。心がマヒしていたようで、あの時の私はどんな感情も湧かなかった。乾いたスポンジみたいな感じだった。重みもない。絞っても何も出ない。
漆黒
世間というものは、弱い者にはとことん残酷だ。
真夜中といっていい時間だった。私はまた色鉛筆とお人形さんを持って、今度は車で移動することになった。暗く曲がりくねった山道だった。街灯などない。頼りになるのは車のライトだけだ。あとは漆黒の闇の中。
人生というのはこういうものか。
元々とても大人びたことを考える子供だといわれていた私は、年齢にそぐわないことをじっと考えながら、この闇はいつになったら明るくなるんだろうと冷静に思っていた。
やがて私は、大人を斜に見る生意気な子供になった。
あれから45年以上経った今でも、自分よりも背が高い男性が怖い。夫になる男性は、私と同じ目線くらいの身長の人にしよう、大きな男が家にいるなんてありえない。ずっとそう思ってた。夢が叶って本当によかったと今しみじみ安堵しているところだ。
-

空腹の少女に パンの耳をくれた ホームレスのおっちゃん
続きを見る