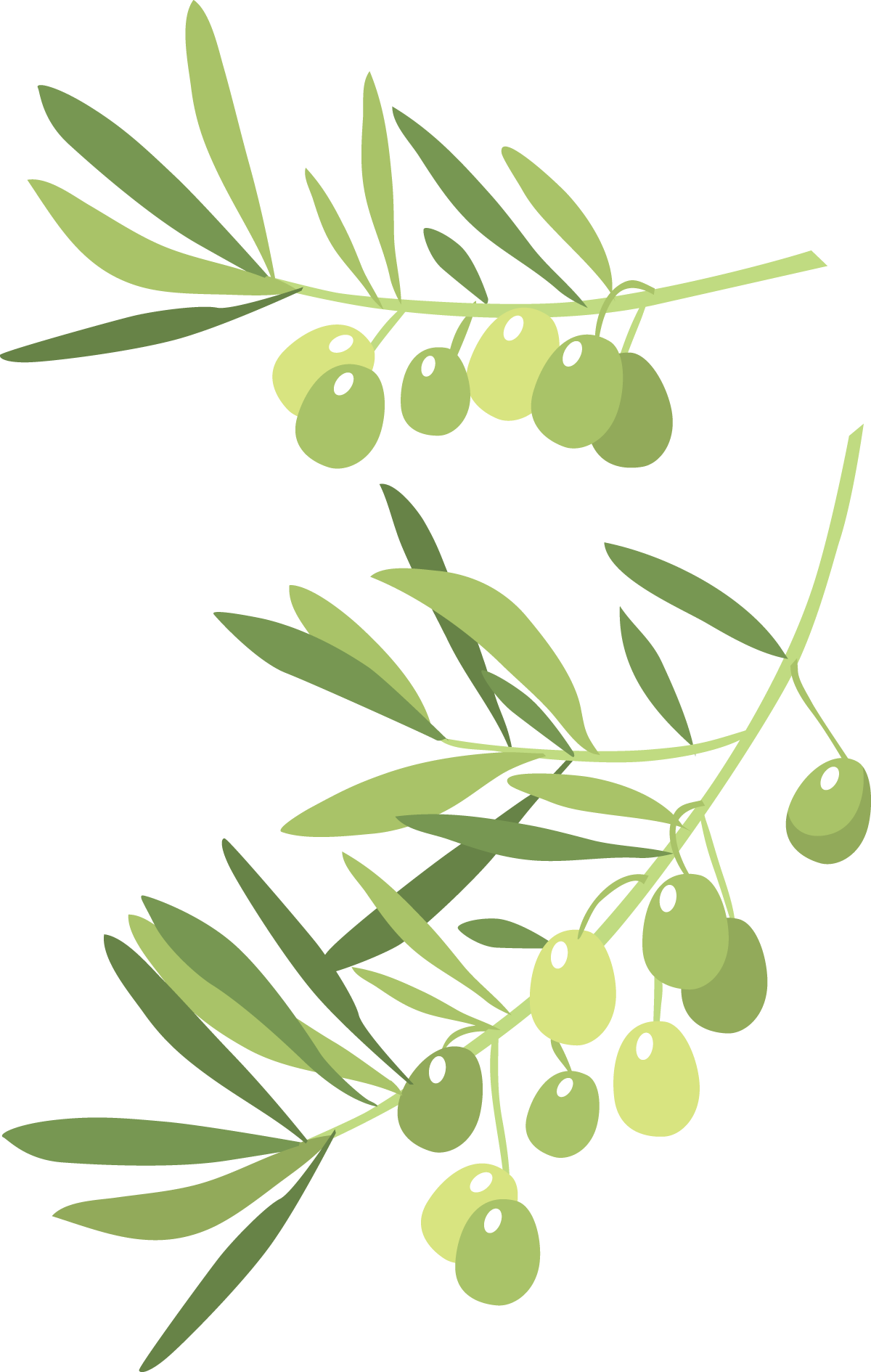段々と空気が柔らかくあたたかくなってきた。もう3月だ。私と弟は別々の家に預けられて冬を越した。けれど、まだ父は病院の中。母はその付き添いで病院にずっと泊まっている。退院はまだまだ先になりそうだった。
私は小学校に通えるんだろうか
小学校に入学する時期がどんどん近付いてきた。小学校からは義務教育だ。どこかに定住して1つの小学校に通わないといけなんだよな。今までのように日本のあちこちを転々とするわけにはいかないぞ。大人達はこれから私をどうするんだろう。
父にはまだ介護が必要で、母は病院で泊まり込みになる。それでも親の近くで学校に通わせたい。そう遠くないところに親戚がいたにもかかわらず、「うちから小学校に通いなさい」と誰も言いださなかったそうだ。
私を押し付け合っている間に刻々と時は流れていく。「子供を病院に泊めてもいいか?」と病院に打診したらしいけれど、「小学生が毎日病室にいるのは困るんですよ」とのことだった。結局、時間切れのような形で、私は小さな家に連れてこられることになった。母や親戚の人が毎日様子を見にきてくれ、時々なら泊まって身の回りの世話をしてもいいとのことだった。
病気は心を壊し、家庭を壊し、子供を無理やり大人にさせる
「親戚は仕方ないとしてもさ。このお母さん、冷たすぎない?」
そう思われることだろう。
きっと母の心は、我慢と悲しさの限界点を越えてしまったんだと思う。夫は3回も脳手術を受けて生死の境をさまよっている。百貫デブと呼ばれてた肥満体の娘は、預け先からえらく痩せて帰ってきた。まともに食べさせてもらえてないことが明らかだ。
頼る先がなく、どうしていいのか分からず、ノイローゼ状態だったんだと思う。
父が元気だった頃の母はこんなじゃなかった。私のことを「おねじょりぽっぽんちぃー♪」と訳の分からない名前で呼び、明るく優しく子供に接する女性だったのに。もう、にこりとも笑わない。
こういう時はむしろ、子供の方が気丈夫だったりする。不幸に関しては大人よりも環境適応力がある。だから、自分が頑張ればそれでいいと思い、自分は当たり前のことをしていると思っていた。
「一人で大丈夫よね?しっかりしてるからお前は」と、大人扱いされてるようで誇らしくさえあったのだから、なんとも悲しい心の背伸びだ。
父方の祖母が家にいたこともあったっけな。でも1カ月後に「心臓の調子が悪くなったから家に帰る」とあっさり家を出ていった。
病気は残酷だ。心を壊し、家庭を壊し、環境を歪め、子供を無理やり大人にする。
小学校で初めてもらった通知表には「言葉がとても丁寧です」と書かれてた。そりゃそうだよ。身体が大きい人には丁寧に接しないと怖いからね。
私を父親に会わせなかった理由
はじめて父と会ったのは、入学式の間際だった。
なぜ真っ先に病院に連れて行かなかったのかと、不思議に思われるかもしれないね。
どうやら父は、3度も頭を開けたり閉じたりしているうちに全くの別人になっていたらしい。精神的にも不安定だった。目が離せない。そんな父親に会わせるのが忍びない、という判断だったようだ。
もちろん「お父さんに会わせて欲しい」と何度か母にお願いをした。けれどそのたびに硬い表情をして「まだあかん」と突っぱねられるばかりだった。
私はこの数カ月で色々なものを見てきた。願っても叶わないことが世の中にはたくさんあることも知っている。これもそのひとつだ。心は乾いていた。
ひょっとするともう、お父さんはこの世にいないのかもしれない。それを私に隠し続けているのかもな。そんなことまで考えていた。
手提げ袋とぞうきんは手縫いのものを準備しろ
入学準備用品のなかに、手提げ袋とぞうきんが必要だと書かれていた。
当時は100均なんてない。縫いあがったぞうきんがスーパーで売られていることもない。アイロンをあてればカバンができる!そんな画期的な商品もなかった。だから幾らお金を出しても手に入らないんだよ、手縫いカバンもぞうきんも。
当時は専業主婦のお母さんが大半だったこともあり、上手下手は別として、手縫いのものを準備するのは当たり前のことと受け止められていた。
私がいたところにはスーパーマーケットと呼ばれる店がなかった。大阪の市街地の話だ。買い物と言えば商店街。布が欲しければ、商店街の布屋さんに行って買わなければならない。
大きな商店街は、父が入院している病院の近くにあった。
買い物に行くで。お父さんにも会いにいこう
「お前が好きな布でカバンを作るから来なさい。筆箱も鉛筆もランドセルも靴も揃えるから」
そう。もう入学間近だというのに、私のところにはランドセルもなかった。今は、夏や秋になると店先にランドセルが並び、おじいちゃんおばあちゃんがウキウキと孫にプレゼントするのにね。ともあれ、久しぶりに母と買い物ができることを、私は心から喜んだ。
そしてもう一つ。
「病室を長く空けるわけにいかないから、布を選んだら病室で縫う。一緒に病室に来なさい。そして、できあがったらランドセルに入れて家に持って帰りなさい」
お父さんに会えるのか!
ランドセルもあるんだね!靴も新しくなるの?窮屈だったんだこの靴。
うきうきと。ただただ うきうきと。
でもその頃の私は、喜怒哀楽の感情を外に出す子供ではなくなっていた。今思い出しても、きゃっきゃとはしゃいだ記憶がない。「わかった」と答えたくらいだったと思う。
「これはうちのお父さん?」手術後の父は別人になっていた
買い物を済ませ、病院の門をくぐった。人工的な清潔さを感じさせるにおいの中、エレベーターの扉が開くのを緊張して待っていた。
病室の入口には、父の名前が書かれたボードがあった。ベッドには全部人がいる。どれがお父さんだ?あれ。どこにもいないじゃない?
母が進むその先に、白い包帯を巻かれたいびつな形の頭をした男の人が座っている。うわ。こっちをみて笑ってるよ。誰よ?私の名前呼んでるで。この人がお父さんなん?お父さん、顔まで手術されたん?顔の半分、動きがおかしいで。
麻痺は顔面にもあらわれていたせいだ。
次に目が留まったのは父の左手だった。明日が手術だという日に、私達をぶら下げて左右に揺らした左腕だ。あんなに力強かったのに。今ではだらりと垂れ下がったまま動かない。あの時「今日で最後になるんやで」と言ってた言葉は本当だった。
何を話したのか本当に一言も覚えていない。その日の父は精神的にも調子がいいようだった。終始穏やかに笑っていた父の顔だけは覚えている。調子が悪い日は荒れて荒れて大変だったようだ。
縫ってくれた布カバンは 卒業するまで穴があかなかった
やがて母は赤地に黄色の花の柄がプリントされた布を取り出し、ベッドのそばでもくもくと布に糸を通し始めた。母は手先が器用な人で、とてもきれいなカバンがみるみる出来上がっていく。ぞうきんもきれいだった。これで汚いものを拭くなんて許せないと思うくらいに。
私はその布カバンを小学6年生まで使い続けた。丈夫だった。それもそのはずだ。手縫いだったのに、ミシンで縫ったように細かくて規則正しい縫い目で、丈夫な当て布も一緒に縫い付けられていたからだ。
子供だけで住んでいる家は そう珍しくはなかったんだよ
「ひとりで子供を住まわせてたなんてウソでしょ?w」そう思う人は幸せな人だ。イヤミで言ってるんじゃないよ。
父が退院した後に引っ越した先では、親が帰ってこなくて子供だけで住んでる世帯は珍しくなかった。だから当時でも、こういう環境で生きてる子は私だけじゃなかった。今でもそうじゃないの?機密性が高いマンション住まいならなおのこと。知らないだけ。見えないだけ。映画や漫画の中だけの存在じゃないんだよ。
私はカップヌードルを食べて生きていた
小学一年生が給食を食べられるまで(午後の授業が行われるまで)1カ月は掛かったかな。もっと先だったのかな。とにかくそれまでは、朝はパンの耳。昼はカップヌードル。夜もカップヌードル。そんな生活をしていた。私が小学校に入学したのは1973年のことで、コンビニなんてなかったからね。
コンビニの日本第1号店は、1971年に愛知県にできたココストア。次に北海道にあるセイコーマート。セブンイレブンの第1号店は1974年に東京でできたんだよ。
調理されたものを子供が簡単に買えるような時代じゃなかったんだ。近所のパン屋になぜかカップヌードルを置いていたので、パンの耳と一緒によく買った。
日清さん、カップヌードルをありがとう
店先に並んでいるカップヌードルは、容器の図柄が(ほぼ)当時のままなんだ。スーパーで見かけるたびに、ひっそりと心の中でつぶやくんだよ。
日清さん。ありがとう。お湯さえ沸かせたら飢えずにすむ食べ物。食べた後は捨てたらいいだけの食べ物。とてもありがたかったです。世に出してくれてありがとう。
-

麻痺した身体で生きている父を 世間は容赦なく笑いモノにした
続きを見る